気管支喘息
気管支喘息とは、気管支の粘膜に慢性的な炎症が起こる病気です。
炎症により気管支の空気の通り道が狭くなると、外部からの刺激に対して気管支が過敏になります。
その結果、咳や痰・呼吸困難・喘鳴などの症状が起こり、それが慢性的に繰り返されます。
治療方法は、発作の頻度や強さによって異なります。
発作の頻度が少なく、症状も軽い咳といった程度であれば、適切に気管支拡張薬を使用します。
そうでない方は、吸入ステロイドなどの治療薬を使用します。
原因
気道の粘膜には、外気の異物を門番として白血球を中心とした免疫細胞が集まっています。
気管支喘息を発症すると、これら免疫細胞がアレルギー反応を引き起こし発作を引き起こします。
気管支喘息ならびに喘息発作を引き起こす原因としては、
- ハウスダスト
- 粉塵
- 運動
- 花粉
- 寒冷刺激
- タバコ
- 煙
- ストレス
- 気候や気温の変化
などが挙げられます。
また、気管支喘息はアトピー型と非アトピー型に分類することができます。
特殊なタイプとして、アスピリン喘息があります。
アトピー型喘息
大人の患者さんの約60%、子どもの患者さんの約90%はこのアトピー型といわれています。
なおアトピー型はアレルギー体質と深く関係しています。
非アトピー型喘息
非アトピー型はウイルス感染などが主な誘因で起こります。アトピー型と違い、アレルギー源を特定することができません。
しかし、気道で起こっている炎症自体はアトピー型と基本的に同じです。このタイプの気管支喘息は大人に多いです。
アスピリン喘息
アスピリン (アセチルサリチル酸)を含む痛み止めを飲むことによって起こる喘息発作です。
成人喘息の約1割がアスピリン喘息であると考えられており、重症化しやすいことも知られています。
症状
喘息は、咳や痰(たん)、息苦しさや「ゼーゼー」「ヒューヒュー」という喘鳴(ぜんめい)など、さまざまな症状があります。
最近では咳だけの喘息(咳喘息)も増加しています。また、胸の痛みやのどに感じる違和感なども喘息の症状のひとつです。
治療せずに放置すると、気道の炎症が悪化して、発作の頻度が多くなったり、症状が重くなったりします。
咳喘息と呼ばれる、咳のみが主症状である喘息が近年多くみられます 。咳は出るものの呼吸機能は正常で、呼吸困難も喘鳴もなく軽い喘息といえます。
しかし、咳喘息の方が気管支喘息になってしまう場合があり注意が必要です。
検査・診断
気管支喘息を疑う場合、年齢や症状に合わせて検査が行われます。
スパリロメトリー
大きく呼吸をしたときに、一秒当たりどの程度の空気を吐き出せるかを調べる検査です。気管支喘息を発症すると、気道が狭くなり、空気を吐き出せる量が減ってしまいます。
血液検査
気道過敏性試験
治療
長期管理薬
発作治療薬
発作治療薬とは、実際に発作が生じているタイミングで自覚症状を改善させるために使用される、より即効性の高い薬です。こちらは吸入薬として使用されることもありますし、貼り薬のタイプもあります。
喘息治療は、長期管理薬を基本として駆使しながら、喘息の発作が生じないような状態にコントロールすることを目標とします。
発作の頻度が数か月に1回という程度であれば、発作が生じたときに適宜吸入薬を使用する対応がとられることがあります。しかし、発作の頻度が多い場合には、適宜長期管理薬の量や種類を増やしながら治療の程度をステップアップさせます。
♦ご予約について
当院は、完全予約制です。
Web予約では事前に問診票をお送りいただくことができるため、当日スムーズにご案内が可能です。ぜひご活用ください。
アクセス
〒541-0052 大阪市中央区安土町3丁目3−5 イケガミビル5階
- 当院には、提携の駐車場や駐輪場はございません。ご来院は公共交通機関のご利用をお勧めいたします。
- 近隣での路上駐車・駐輪はご遠慮ください。これにより生じたトラブル(盗難や事故、撤去など)に対して、当クリニックは一切責任を負いかねます。
【御堂筋線・中央線・四つ橋線】 本町駅3番出口 徒歩2分
【堺筋線】堺筋本町駅17番出口 徒歩6分
各駅からの経路についてはこちらのページをご確認ください。
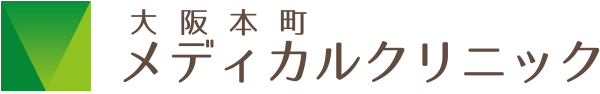
 050-3161-5913
050-3161-5913
