「眠り方が分からなくなった」と不眠恐怖を抱く慢性不眠の方への対応

成人の3人のうち2人が睡眠に関して悩んでいる
不眠は極めて頻度の高い症状であり、現在成人の3人に2人が睡眠に何らかの悩みを抱えているといわれています。
そのため、すべての診療科において臨床で問題となることが多いです。
最近は安全性の高い睡眠薬も増え、一般医が処方する機会も多くなりましたが、依然として睡眠薬には過鎮静や転倒リスクに加えて、精神依存や身体依存の問題があり、むやみに処方するのは好ましくないです。
ICSD-3の不眠障害の診断基準にあるように、診断には夜間の不眠症状に加えて、日中の機能障害を伴わなくてはなりません。
「早朝覚醒」しているケースも
十分な睡眠時間が確保できているにも関わらず、寝つきが悪いことを不眠と訴えるケースや、就寝時刻が早いゆえに早朝覚醒しているケースも少なくはないでしょう。
そのため、具体的な睡眠状況を明確にするためにも、睡眠行動日誌の活用が有効です。
睡眠行動日誌には、ベッドに入る時間、就寝時間、起床時間、中途覚醒時間、日中の眠気などを詳細に記載します。
日誌を踏まえ、睡眠状況を把握できたのち、不眠の原因について検討します。
環境の変化や精神的ストレス、痛みや咳などの身体的ストレスがある場合は、一過性の不眠は自然な反応と考え、原因除去が優先されるでしょう。
また、ステロイドなどによる薬剤性不眠や、うつ病やむずむず脚症候群などの不眠の原因となる他疾患の有無も確認する必要があります。
原因がすぐに除けない場合は、対症療法として一時的に睡眠薬を使用します。
「慢性不眠」とは
一方、原因が除去された後も不眠症状のみ持続してしまう場合があり、これを「慢性不眠」と呼びます。
慢性不眠の治療には、睡眠衛生指導が欠かせません。
なぜならば、前駆した急性不眠エピソードの時に、睡眠に対する誤った認知や行動が習慣づけられ、それらが持続することで慢性化しているケースが多いからです。
睡眠衛生指導の必要性
患者さんは不眠を夜間のみの問題として捉えることが多いですが、一日を通した生活指導が必要です。
不眠は強い不快感を伴うため、不眠恐怖に移行しやすく、正しい知識提供に加えて患者さんの苦痛に共感し、安心感を与えることも大切です。
これら睡眠衛生指導の内容については、睡眠の認知行動療法 CBT-iが推奨されており、その有効性が示されています。
一般医にとって認知行動療法は、精神科特有の治療法のように認識されがちですが、その内容は難しいものではなく、あらゆる場面で応用できるものです。
睡眠薬の処方に先立ち、睡眠衛生指導も行っていきたいと考えています。
日々の生活で睡眠の質を上げる
睡眠衛生指導のほか、厚生労働省による健康づくりのための睡眠指針として「睡眠12ヶ条」を提唱しています。
その中でも、今からできる対策も多くあります。
・規則正しい3度の食事、運動習慣
・同じ時刻に毎日起床
・自分なりのリラックス法をみつける(音楽、ぬるめの入浴など)
体をリラックス状態にすることは快眠にもつながります。
まずは今からできる対策をはじめることをおすすめいたします。
当院のある同じビル内、3階にある【快眠ほぐしサロン「すいみん」】
『睡眠・快眠特化型のサロン』としてセラピストによるカウンセリングと睡眠衛生指導をミックスさせてその方に合った快眠プランをご案内しております。
ぜひ一度ご体験してみてください。
快眠ほぐしサロン「すいみん」はこちらから
診察のご予約方法
監修者情報・医師 松島勇介

日本睡眠学会専門医
日本内科学会認定内科医
日本医師会認定産業医
日本消化器病学会専門医
日本消化器内視鏡学会専門医
厚生労働省 オンライン診療研修修了医
こちらの記事は松島勇介医師監修のもと作成しております。
入眠障害の方は受け付けておりません
入眠障害の方はこちら
本町の内科・睡眠科は大阪本町メディカルクリニック
大阪市中央区安土町3丁目3−5 イケガミビル5階
TEL 050-3161-5913
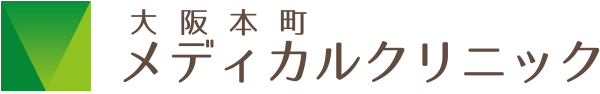
 050-3161-5913
050-3161-5913

